第20回愛媛社会科・主権者教育研究会成果報告

2025年5月30日(金)に第20回愛媛社会科・主権者教育研究会が愛媛大学教育学部にて開催されました。今回は、松山市立城西中学校の髙岡遼介先生と東温市立重信中学校の木下博斗先生より、令和6年度に取り組まれた社会科授業研究の成果についてお話をしていただきました。その上で、資質・能力育成につながる授業づくりの視点や方法、授業改善の方向性について意見交換を行いました。
まず、髙岡先生より教師という仕事と授業づくりを行う上で大切にしていることについての説明が行われ、公民的分野における主権者教育の授業実践についての報告がありました。
選挙年齢に達していない中で主権者としての自覚を持ち、社会と関わろうとする子どもの育成を目指し、年間の授業を通して継続的に行う①みんなが安心して使える公園、②絵本を活用した授業、③道路拡張計画、④松山市のまちづくりについての4つの実践が提案されました。
さらに、授業改善に対して難しく捉えすぎず、研究会の授業を真似すること、1年間の授業で1単元は授業改善を行うこと、大学を活用することの3点を意識しながら無理のない程度で行うことの重要性についてのお話がありました。

(髙岡先生ご発表の様子)
次に、木下先生より地理的分野、歴史的分野、公民的分野の各分野の繋がりに対する課題意識から、社会問題を歴史や地理の学習の中でどのように取り扱っていくのかということを意識した授業づくりについての説明がありました。
そのうえで、論争性のある社会問題について地理的な議論を行うために、地理的分野の「アフリカ州」で行ったオリンピックを題材としたアフリカ州の単元モデルが提案されました。

(木下先生ご発表の様子)
2人の先生の報告後には、グループに分かれて「資質・能力育成につながる授業づくりの視点や方法」や「授業改善の方向性」、「報告を受けての疑問点」などについて意見交換を行いました。
参加者の主な意見は以下の通りです。
・単元を意識しながら1つの授業を作っていく重要性や当たり前を疑うことを知ることができた。また、授業作りに追われる中で、意識しなければならないことを再確認できた。
・単元や年間を見通した計画的な授業の構成と、目指したい姿、身に付けさせたい力をイメージすることの大切さを改めて感じました。
・中3でいきなり公民の授業を取り扱うようになって、子どもたちに公民の学びの重要性を感じてもらうのが難しい中で、実際にある問題を加工して分かりやすくしたり、自分たちで考えた意見が社会に実際に繋がっていくということを実感してもらうなど、様々な角度からのアプローチが教師にはできるということを学べた。

(意見交換の様子)
髙岡先生はミドルリーダーとして、木下先生は若手教員としてそれぞれの立場だからこそできた社会科授業づくりの視点や方法についてのご発表をしていただきました。社会の変化に伴い、教育現場でもさまざまな変化が起こっている現在、教師として何が求められ、何ができるようになる必要があるのかということについて改めて深く考えるきっかけになりました。
平日にもかかわらず、現職の先生方にも多数ご参加いただき本当にうれしく思いました。関係者の皆様、ありがとうございました。
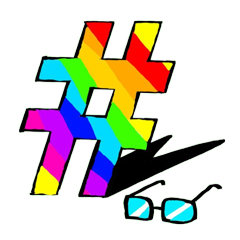 愛媛大学井上昌善研究室
愛媛大学井上昌善研究室 愛媛大学
愛媛大学  ゼミ紹介動画
ゼミ紹介動画