多様性に着目した教育プログラム
第1回 意見交換会
2025年5月22日に、愛媛大学にて石井北小学校で実施された「性の多様性」を主題とする単元についての意見交換会が行われました。本会には石井北小学校から仙波先生、岡部先生に来ていただき、学部3回生2名と大学院2回生1名が参加しました。お二方の先生より、①実施した授業の内容について、②継続して「性の多様性」を主題とした授業を実施できた背景についてお話いただき、その後、授業改善の視点からの意見交換を行いました。
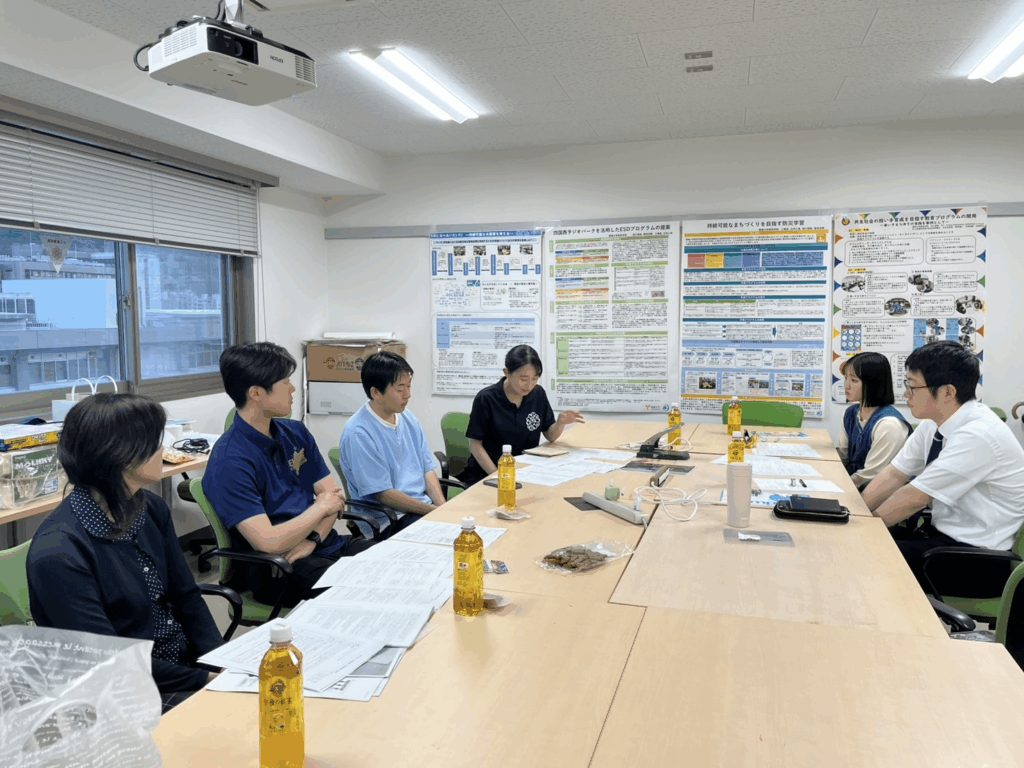
(意見交換会の様子)
石井北小学校では、令和3年度より総合的な学習の時間で「性の多様性」を主題とした単元を、継続的に取り組んでいます。本単元は、児童の実態を踏まえ、性的マイノリティに対する受け止め方や理解の変化に応じて内容を柔軟に改善しながら展開されてきました。このような実践が継続されている背景には、学年部において「性の多様性」に関する教育の意義が共有されており、継続的な取り組みの重要性について教職員の間で高い意識が保たれていることが挙げられます。さらに、本単元は参観日にも実施されており、児童の学びの様子を保護者に公開することで、家庭への理解の波及も図られています。子どもたちの成長する姿を通して、保護者にも多様性への理解が広がることを目指して、学校と家庭が連携して学びを支える体制を築かれてきたことが明らかとなりました。
この報告を受けて、学生からは、「こうした性の多様性を受容とする姿勢が子どもたちからは見られたが、実際に社会で見られる性の多様性に関しての社会的な論争問題についてはどのように受け止めているのか、また、それらは授業で取り扱う場合にはどういったことに留意すべきか」という質問が投げかけられました。この質問を通して、社会的な論争問題の解決を目指すといった授業は困難かもしれないが、子どもたちが「ちがいを認められない自己」を自覚することができる学習活動を組織することが必要ではないかという授業改善の視点が投げかけられました。また、こうした学習活動を組織するにあたって、「ちがいを認めあうことは大切だとわかっているのに、なぜちがいを認め合えないときがあるのだろう」と発問することを通して、自分たちの持つ価値基準は社会規範やメディアの影響を受けて構築されてきたことを理解できるようにすることが重要ではないかという意見も出されました。さらに、こうした「影響を受ける私」だけではなく、影響を与えられている社会規範やメディアに対しても、自分たちの働きかけによって影響を与えることができることについても理解を促していく必要があるのではないかとありました。このように「影響をうける私」、「影響を与える私」というアイデンティティの二面性を自覚させることが、共生社会の実現に寄与する市民の育成を促すのではないか、という授業改善の視点が提案されました。こうした議論を受けて、教材研究にあたっては、問題解決のために奮闘する当事者だけでなく、その解決に寄与することのできる周囲の人間に着目して、そうした解決の伴走者になるための条件について分析することが必要なのではないか、という新たな視点も提示されました。
今回の報告会では、「性の多様性」を主題とした単元を実施するための学校マネジメントのあり方、そして、授業改善の視点や方法について考えを深めることができました。継続して、石井北小学校の実践について意見交換をさせていただけたらと思います。
関係のみなさま、お忙しい中、貴重な機会を設けてくださりありがとうございました。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
マイノリティの地域共生・社会参加 ①
本日(6月13日)、松山市人権・共生社会推進課の方々をお招きし、マイノリティの地域共生・社会参加に関する人権問題をテーマにして話し合いが行われました。
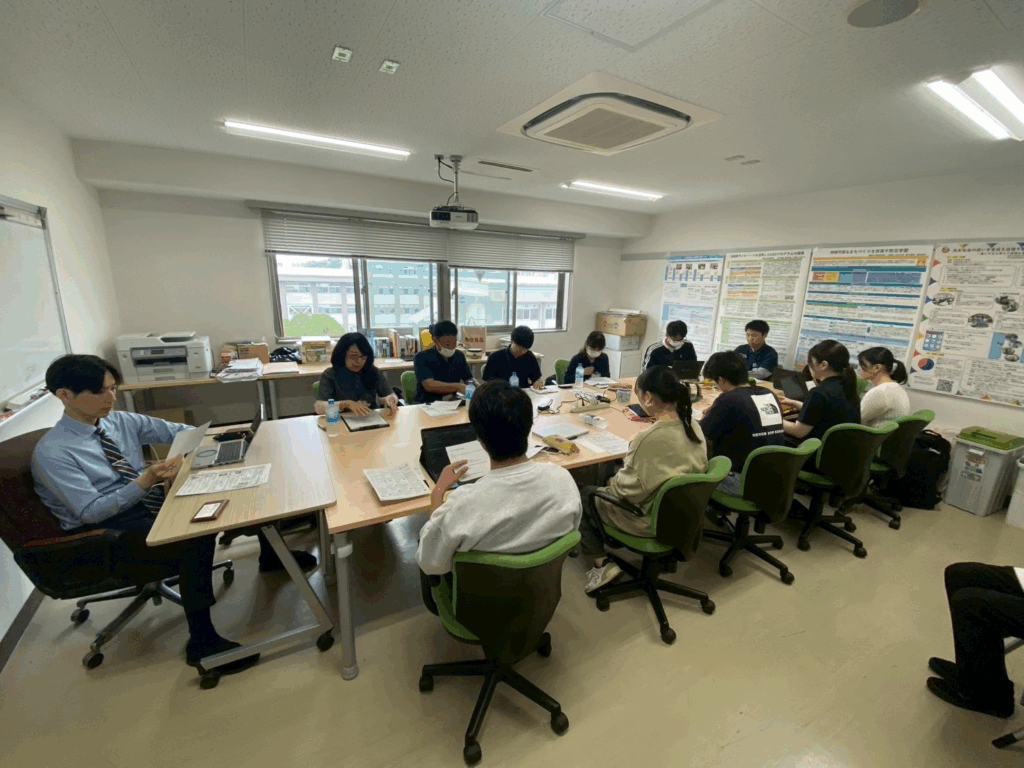
(活動の様子)
まず、人権課の方から、障害を持つ方の事例をもとに四つの視点をいただきました。一つ目は、二律背反の葛藤があるということです。二つ目は、見えない差別があるということです。具体的には、障害者の方が、健常者に気を遣い、希望していた行動を自らとらなかったという事例を挙げていただきました。三つ目は、共生社会の実現という理想はもっていても、それを実行していく難しさがあるというように、理想と現実とのギャップが大きいということです。四つ目は、逆差別があるということです。逆差別とは、特定の集団を優遇したことで起こる諸問題や不公平を批判した言葉です。
以上のようなお話しをお聞きした後、話し合いを行いました。その話し合いの中では、「障害者はみんなと違う・障害者はかわいそうという考え方を変える必要があり、そのためには実際にコミュニケーションをとることが大事。教育でそういった場を作るべき。」という意見や「ケア体制の充実が求められている中で、ケアをしたくてもケアの仕方が分からないという人が多いのではないか。障害者の方からお話を聞く機会はあると思うが、障害者をサポートしている方のお話を聞く機会は少ないので、そういった機会を増やしていくことで、ケアの方法を知ることができ、ケア体制の充実が実現できるのではないか。」というような意見が共有されました。
本日の経験は、共生社会の実現に向けて改めて考えるきっかけになりました。障害の捉え方を「医学モデル」から「社会モデル」に換えていくことが必要であり、そのための教育について今後も考え続けたいです。私も共生社会を実現したいという願いはもちつつも、現実との行動にギャップが生まれることがあると再認識させられたので、今後は意識して生活していきます。本日は貴重なお話をありがとうございました。今後もよろしくお願いいたします。
次回は、6月4日(金)に人権啓発にかかわる紙芝居をご紹介いただく予定です。
同和問題・人権教育
本日(7月4日)、松山市人権・共生社会推進課の方々をお招きし、「いのちをいただく」、「みつこの詩」という紙芝居をご紹介いただきました。
「いのちをいただく」とは牛の屠殺場で働く坂本さんのお話です。屠殺業の重要性や屠殺業を営む人の苦悩について描いたものでした。屠殺業を営む人は、長年、被差別部落に住み、身分差別を受けてきました。いのちの大切さ、被差別部落について学べる紙芝居であるとご紹介いただきました。また被差別部落は差別されてきた一方で、歌舞伎や能などの文化を育んできた立役者でもあります。教育において、同和問題を取り上げる際には、教師自身が正しい知識をもつことが必要であると感じました。
「みつこの詩」とは水俣市明神町に嫁いだみつこさんのお話です。夫と義父を水俣病で亡くしたみつこさんの生涯を描いたものでした。水俣病は感染するとされていて、水俣病患者及びその家族は差別を受けてきており、今でもその差別に苦しんでいる人もいます。また、水俣病の問題は、行政や漁協が風評被害を防ぐために情報を隠してきたところにもあるそうです。教育において水俣病を取り上げる際には、差別問題だけではなく、社会問題や社会制度まで言及する必要があるのではないかと考えました。
どちらのお話も人権にかかわる問題を学べるとともに、差別を受けてきた人々が強く生きる姿をみることができました。今後は、この紙芝居を用いて授業を開発していきます。差別を受けてきた人の実態・心情等をしっかり見とり、正しい知識をもって授業を構成するとともに、社会問題・社会制度につなげる授業が開発できるよう、研究室一同教材研究に努めます。
改めて人権問題・同和問題について考える機会になりました。貴重なお話をありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。(報告者:大石有美香)
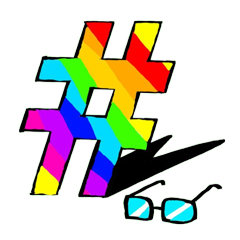 愛媛大学井上昌善研究室
愛媛大学井上昌善研究室 愛媛大学
愛媛大学  ゼミ紹介動画
ゼミ紹介動画